教員採用試験が6月に変更というニュースに関して記事を書いてからしばらく経ちました。
参照 2024年から教員採用試験が6月に変更 現場のことを理解しているか疑問
福岡県の状況がニュースで入ってきました。
結論として、志願者数は前年度に比べ110人減るという結果となりました。
そのほか、全国でいち早く教員採用試験を実施した静岡県に目を向けてみました。すると去年より5名増加したそうです。
つまりどちらの県も、多少の増減はあったものの「誤差の範囲内」であると当サイトは考えました。
よって、6月の前倒しは今回の結果から見ると、あまり意味のあるものではなかったといわざるを得ません。
教員採用試験の時期が問題ではない 誰もが予想した結果
内定の時期が教員希望者の減少の一端を担っているようなニュースを見たことがあるのですが、それが原因ではないということは多くの現場教員、そして教育関係者はわかっていることです。
わかっていないのは、ルールを決める人たちだと思います。
ルールを決める人たちを擁護するならば、教員希望者の減少に歯止めを効かせるべく何かしらの手を打たないといけないと考えており、手あたり次第、思いつく限りを試しているのかもしれません。
そもそもですが、大学生の内定の時期は7月~12月の間くらいです。
採用試験の時期を早める前までは、最終結果がわかるのは大体10月~11月あたりでした。つまり採用試験の時期を早める前からも、発表時期が遅すぎるということはないのです。
ちなみに今回時期を早くし、福岡県の教員採用試験の1次は7月9日(日)。静岡県は最も早く1次試験が5月11日(土)12日(日)とのことです。
そして静岡県に関しては、2次試験の発表は8月9日(金)の予定となっているようです。
労働環境が問題 そこに手を付ける必要がある
いくら教員採用試験の時期を早くしたとしても、教員の志願者はあまり増えないと思います。
なぜなら教員志望が減少している理由は、志願時期ではないと思うためです。
総合的にいうと「労働環境が問題」となっているためです。
ズレた改善案 残業代を4%から10%に上げるのはズレている
先日、中央教育審議会が教員の残業代を4%から10%に引き上げるという素案を示したという記事を書きました。
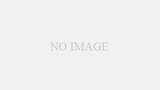
そこで当サイトの考えとして、「悪い案ではないが順番が違う」「教育現場を理解しているのか疑問」という内容の記事を書きました。
昔からいえることなのですが、教育関係のルールを決める人たちは、どうしても現場の実情に沿ったルールを出せないように思えます。
あくまでも推測なのですが、ルールを決める人たちは教育現場を経験したことがないのだと思います。もし経験しているのであれば、採用試験の時期もそうですし、残業代に関しても、このような案を出せるとは思えません。
採用試験を早めるメリットは暑さ対策くらい
教員採用試験が早まったおかげで、暑い時期から逃れることができたのはメリットだと思います。
教員採用試験はこれまで夏の暑い時期に行われてきました。
あくまでも私の経験上の話ですが、面接前には体育館で待たされた記憶があります。体育館の窓は開けられていたのですが空調設備がなく、とても暑い中、長い時間待ったのです。
それも試験であるため、皆スーツ姿です。大量の汗をかきながら長時間自分の順番が来るまで待つのはかなりきつかったです。
しかし採用試験の時期がずれることで、もっとも暑い時期からズレることにはなりました。その点はよかった点かもしれません。
倍率を高くしたい理由 優秀な人材を確保したいから
教員採用試験の倍率は1倍を切っているわけではありません。
しかし教員不足という話をよく耳にします。
教員不足というのは「講師不足」という意見も聞かれます。確かに講師は必要ですし、不足していると思います。
勉強ができるから良い先生とは限らない そこを認識するべき
まず採用試験の倍率が1倍を切っているわけではなく、少しでも倍率を上げたい理由は「優秀な人材の確保をしたい」と考えているからでしょう。
多くの志願者がいればいるほど、優秀な人材を見つけやすいという考えです。
しかしその結果、昨今報じられる教員の不祥事。もちろんすべての先生が不祥事を起こしているわけではなく、ほんの一部の人たちの事件かもしれませんが、採用試験の内容に疑問を持たざるを得ません。
先ほどもお話ししましたが「少しでも優秀な人材を確保したい」という、採用側のいやらしさを感じます。
ちなみにここでいう「優秀」とは、試験の点数で高い点数を取れる人のことです。
わかっていないと思うのは、試験結果と教育は比例するようでしないという点です。
また教員という仕事がそこまで人気のある職業ではないということをしっかりと認識したほうがよいと思います。
高学歴が先生になったのを見たことがない
またそもそもですが、優秀な人材は先生にはなりません。ほかの仕事を選びます。
私だけかもしれませんが、たとえば優秀を学力と捉えた場合、偏差値70以上の大学卒業をして教員になった人を見たことがありません。
もちろん高学歴で先生になっている人もいるとは思いますが、そうではない人の方が多いと思います。
講師不足を解消するべき 講師の扱いをもっと優遇する必要がある
教員不足の一端を担っているのは講師不足だと思います。
参照 学校の教員不足の根本的な原因は「講師不足」 制度的に問題があるため講師の扱いをもっと良くするべき
産休、育休、病欠の先生の代わりに入ってくれる講師は、学校にとって非常に重要な存在です。
しかし教諭の中には講師を下に見る人も多いです。また扱いも教諭は昇級し続けるのに対し、講師の給与は上限が決められています。
そんな中、喜んで講師になってくれる人は本当に先生という仕事が好きな人なのです。
それなのに前述したような扱いを受けるのであれば、誰も講師として働こうとは思いません。
そういったところが治っていないから、教員不足という結果になっているのです。
まとめ
ここまではあくまでも当サイトの意見です。
当サイトの管理人は学校現場で働いていた経験を持っています。その経験をもとに記事にしていますので、あながち適当に書いているわけではありません。
私は学校の先生の仕事が好きでした。
今でも副業でOKというのであれば、現場に戻ってもよいとは思っています。
それくらい好きな仕事です。
しかしだからこそ、悪い所に目が向いてもしまいます。
現場がわかっている人たちがルールを決めるべきだと思います。
