通信大学で教員免許を取得した場合、学校現場で不自由に感じることがたまにあります。それは、「ほとんどの教員は教育学部を卒業し教員になっているため、教員免許の取得方法が異なっていること」です。
つまり、普通の大学と通信大学での教員免許の取得方法が異なってくるのです。もちろん教員免許自体は全く同じものです。違いはありません。
たとえば、小学校の教員同士の会話で次のようなものがあります。
「私の専門は数学なんだけど、君は何だったの?」
通信大学で小学校の教員免許を取った場合、とくに専門と言うものはありません。そのため
「通信で教員免許を取得したため、専門はありません。」
このように返すことになります。
とくにこのこと自体は不自由に感じることはないのですが、周りの教員とは違った経路で教員免許を取っていると、周りの教員が当然のように知っていることが講師は知らないということが出てくるのです。
採用試験に合格すると初任者研修がある 講師にはない
教員採用試験に合格した人は、はじめの1年間、初任者研修というものを受けることになります。
指導教員が付き、クラス担任をしながら1年間で先生のイロハを教えてもらうわけです。
そこで1年かけて、一人の教員ができ上っていきます。
しかし講師にはそのような機会はありません。誰にも何も教えられることなくクラス担任がいきなりはじまることもあるのです。よって自分で考え、わからないところは積極的に聞いていくしかないのです。
よって正規教諭と講師の間には知識の差が生まれることがどうしてもあるのです。
人気の講師もいる
講師は研修というものがあるわけではありませんが、それでもうまく対応している人も多くいます。
積極的に学校内の先生とコミュニケーションを取り、何をどのようにすればよいのかを自力で学んでいきます。
指導案の書き方
通信大学で教員免許を取得し、講師として学校で働く先生のほとんどが困ること。それは「指導案の書き方」でしょう。
講師と言えど担任を持っていると、指導案を書くことがあります。たとえば、教員採用試験に合格していれば、初任者研修で大量の指導案を書くこととなります。
また、普通の大学の教育学部に通っている経験を持っていれば、大学で若干なりとも指導案を書く練習を行うことでしょう。
ところが、通信大学で教員免許を取得しているときに指導案を書く練習は行いません。唯一、教育実習の時に、数枚書く程度です。
参照 教育実習は通信大学でも必須!教員免許を取るなら絶対に参加しなければならない教育実習
そのため、「今度の授業参観のために指導案を書いてください」といわれても非常に困ってしまうのです。過去の指導案を色々参考にしながら書くのですが、何が何だか良く分かりません。かろうじて出来上がったものを、学年主任に提出しても、大抵NGを出されます。
また、指導案を書くソフトが、当時は「秀丸」が主流でした。全く使い方が分かりません。最近ではワードを使用する学校も多くなってきましたが、年配の先生は秀丸を愛用していたため、それに合わせなければなりませんでした。
1枚の指導案を完成させるのに、考えられないくらいの時間を費やした記憶があります。
慣れが必要
指導案を書くことは正直慣れが必要だと思います。
逆に慣れてしまえば、ある程度スイスイ書くことができます。
また慣れているベテラン教員でさえも、他の先生からダメ出しを食らうこともあります。
よって周りの先生に聞きながら、自分なりの指導案を作成すればよいと思います。
授業の仕方
通信大学では教員免許を取得するための単位を修得するだけです。
その中で授業の仕方を勉強する科目は、正直記憶にありません。ただし教育実習では少し授業を行うことができます。しかしその程度です。
採用試験に合格した初任者の場合は、指導教官が付き、授業の仕方を手取り足取り教えてくれます。しかし、講師の場合は基本的に誰も教えてくれません。
突然本番がはじまるのです。
そのため自分で試行錯誤しながら授業を行っていく必要があります。
大抵、学年部で「今週、この教科はこのくらいまで終わらせよう。」といったことを学年会議で決めます。そのため、逆算しながら1日どのくらいのペースで授業を行っていけばよいのかはなんとなく分かります。
ただし、どのように授業を行えばよいのかは手探り状態です。そのため、「自分が小学校の時に、こんな感じで授業を受けたよな・・・」という薄い記憶を辿り、授業を行っていくことになります。
このようなことがある為、少しでも時間が空くようなことがあったら、誰でもよいので、授業見学をさせてもらった方がよいと思います。
解決方法としては、学校内に保存されている指導案を参考にしてみることでしょう。上司の先生にお願いすれば出してくれると思います。どのような形式で書けばよいのか、どのような流れを作ればよいのかは多少なりとも理解できるようになると思います。また分からないことは先輩の先生方に質問してみるとよいでしょう。
わからないから吸収する
あくまでも経験談ですが、誰にも授業の仕方を教えられないと必死になるものです。
- 生徒に伝わっているか
- 生徒はどのような反応を示すか
- 何を話せば響くのか
さまざまなことを肌で感じ、生徒のことをよく観察するようになります。
すると、指導教官に教えてもらって型ができ上っているよりも、面白い、そして生徒に伝わる授業ができるのではないかと思います。
全員とはいいませんが、本当に上手な授業を行う講師の先生も意外といるものです。
校務分掌の仕方
校務分掌とは、学校運営をするために必要な業務です。よく「分掌」と呼ばれます。
たとえば、「生徒指導部」や「交通安全」など、かなりの数あります。そして、それぞれに代表者が付き、関連各署と連携を取り運営を行っていきます。
大きな学校の場合、正規の教諭がそれぞれの文章の代表になるので、講師はとくにすることがなかったりします。また、1人の教諭が複数を掛け持ちしたりします。
ところが、小さな学校や、所属している教諭が忙しかったりすると、講師だとしても公務分掌の責任者になることがあります。
たとえば「交通安全」の責任者になったとしましょう。この場合、地域の警察と連携を取らなければなりません。たとえば低学年の交通安全教室や自転車教室と言った行事がありますが、これらの日程の調整をする必要があります。もしこれらの調整を忘れていたりすると、行事自体ができなくなってしまう可能性もあります。
そのため、関係各所と連絡を取ったり、決まったことを職員会議で発表したりするわけですが、関係各所といつ連絡を取ればよいのか、全く分からないのです。
分からないことは、先輩の教諭に基本聞けばよいのですが、聞いてもしっかり教えてくれる人もいればそうでない人もいます。それに毎回聞くのも気が引けます。ただ、しっかりと予定を組まないと、後で非常にまずいことになるので、何度も何度も分からないことは聞きに行くしかありません。
このように、後半は講師の事になってしまいましたが、全体を通して言えることは、通信大学では、完璧には先生のイロハを学ぶことができないということです。そのため、持っている教員免許は同じだとしても、一般の教諭に追い付くためには、学校現場でも相当の苦労をしなければなりません。
「分からないことは聞く。何度も何度も聞く。聞きづらくても聞く。」
これを頭の隅に置いておいた方がよいと思います。
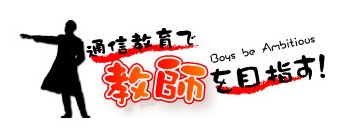



取得できる通信大学を検索
取得できる通信大学を検索