「先生が嫌いだから、勉強が苦手」
という話を聞いたことはないでしょうか。
実際に良くある話です。
長い間、子どもにモノを教える仕事をしていると、「覚える力はあるのにもったいない・・・」と思うことがよくあります。
理由はさまざまですが、「学校の先生が嫌いだから勉強したくない」といったことがよくある理由の1つとなります。
今回は「能力はあるのになぜか身に付かない」といった事例をお話したいと思います。
能力は問題なし 問題は興味・関心
私は勉強に一番必要なものは「能力」と「興味・関心」だと思っています。
まず「能力」ですが、今回は「記憶力」を指したいと思います。
勉強をするということは、一定の記憶を脳の中に入れるということです。インプットですね。
この記憶力には当然個人差があり、1回で覚えられる子どももいれば10回かかる子どももいるし、100回かかる子どももいるかもしれません。記憶力に関しては平等ではないと言えるでしょう。
なので、記憶力がよい子どもの方が、勉強が得意になりやすいものです。
興味・関心が大きく関わる
記憶力がよい子どもの方が勉強が得意になりやすいことは事実です。
ただしものすごく記憶力がよい!という子どもに出会ったことはほとんどありません。長く教育に携わっていますが、ほんの少数です。
ものすごく記憶力が良くなかったとしても、勉強ができる子どもはたくさんいます。
記憶力には「興味・関心」が大きく影響します。この典型例が「ゲーム」や「アニメ」です。
あまり勉強が得意でない子どもでも、ゲームやアニメの詳細を覚えていることが多々あります。
理由は「興味・関心があるから集中力が増し、記憶へと繋がっている」ためです。
つまりどのような事であったとしても、興味・関心を持たせることができれば、モノを覚えることはそこまで難しいわけではないのです。
能力が高いのに成績が悪かった事例
では実際にあったお話をしたいと思います。
ある中学生の話です。その子に携わっている塾の講師は口を揃えて言います。
「覚える能力は他の子を圧倒している。それなのに成績が芳しくない。」
覚える能力が高い、つまり記憶力はよいのですが、なぜかテストの点数が思うように取れないのです。平均点を下回ることもよくあります。
しばらくその子を授業で見ていて、その原因をいくつか発見しました。
短期記憶は鋭いが、長期記憶に至っていない
1つ目の問題としては、「短期記憶は鋭いが、長期記憶に至っていない」と言うことです。
「塾と学校との壁」でも触れましたが、記憶には短期記憶と長期記憶というものがあります。基本的に勉強をしていて「覚えた!」と言うのは短期記憶と考えてよいと思います。
「この間覚えたのに・・・あれ?なんだっけ?」と言った経験があると思いますが、しっかりと身に付ききれていないのです。何度も反復を繰り返すことで、長期記憶に移行します。すると忘れにくくなります。
この子の場合、短期記憶の能力が高く、すぐに授業の内容を理解することが出来ました。そしてその子自身も「もう覚えた。大丈夫。」と思っていました。
しかししばらく時間を空けると忘れてしまい、テストで点数を取ることが出来ないでいました。
この解決法は簡単ですね。反復練習をすればよいだけです。そして、その子自身にも、何度か繰り返さなければいけないと伝え、徹底させればよいのです。
先生が嫌い
ただし2つ目の問題が、大きな障害となりました。
塾に来ているときにはしっかりと勉強をします。しかし、家や学校では勉強をしないのです。そのため、反復練習をする時がないのです。
「なぜ塾以外では勉強しないのか?」
単に面倒だからかと思っていたのですが、実は原因はそれ以外にありました。
ある日、もしかしてと思い聞いてみました。
「もしかして学校の英語の先生、嫌いなんじゃない?」
とくに英語が苦手だったので、物凄くストレートで失礼な質問かもしれませんが、直球で聞いてみました。すると、
「英語の先生、気持ち悪いんだよね。大嫌い。」
とこれまた直球で帰ってきました。これが全ての答えだと分かりました。
教育者は嫌われてはいけない
人間好き嫌いがあります。それは仕方のないことです。
しかし、「嫌い」になることはそれほど多くはありません。
その子にとって英語の先生は「嫌いな存在」になってしまっているのです。
嫌いなため授業を聞きませんし宿題もしません。そのためいくら記憶力がよかったとしても、記憶が定着することはありません。
ハッキリ言います。先生は嫌われてはいけないのです。
嫌われない努力をしなければいけませんし、嫌われないようにすることはある程度は可能なのです。
嫌いになる理由は意外とシンプル
その子が先生を嫌いな理由は単純でした。独り言を言っていることがあるということなのです。
確かに独り言をブツブツ言われたら、大人からしても良くは思いませんよね。子どもは感受性が豊かです。「こういった人もいるんだなぁ」なんて、心を広くできるものではありません。
嫌われないようにするためには
別に好かれる必要はありません。嫌われなければよいのです。勿論好かれた方がよいのですが・・・。
では「嫌われないようにするにはどうしたらよいのか?」ですが、2つの方法があると思います。
1つは、「子どもに嫌がられるようなことをしない」と言うことです。当たり前だと思われると思いますが、これが重要です。
たとえば独り言。確かに嫌ですよね。髪型がボサボサ。とくに女の子からすると嫌がられるかもしれません。その他、服装、口臭、体臭、態度・・・。いくらでも挙げられます。それを1つずつ潰していけばよいのです。
その際、自分ではなかなか気づきにくいかもしれないので、周りの人に指摘してもらうとよいでしょう。その際に悩みを正直に言った方がよいです。
もう1つは、「嫌いを凌駕するような好きなポイントを作る」と言うことです。
たとえば、子どもが好きそうなテレビやアニメに詳しくなるとか、授業中にたまにくだらない笑いを入れたりすることです。
子どもが先生を嫌いになる理由は非常に些細なことです。しかしそれがその子どもの成績にまで影響するのも確かです。
勉強ができないで困るのは子どもではありますが、ちょっとした先生の努力で授業の雰囲気も変わりますし、子どもの成績も向上します。
大学や通信大学では教えてくれない!?
今回触れたことは、教育現場では非常に重要なことです。
もしかしたらTOP3に入るくらい重要なことかもしれません。
しかしこのようなことを通信大学で勉強することはありませんでした。一般的な大学の教育学部でも、このようなことを教えているかは疑問です。
学問的な知識を身に付けることは重要です。しかし人間相手の商売をするのであれば、人間に好まれる方法を勉強する必要があるかもしれません。
好まれずとも嫌われない方法を知っておいた方がよいでしょう。
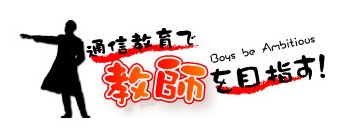



取得できる通信大学を検索
取得できる通信大学を検索