学校教育の基本は、「どの子どもも平等に対応する」でしょう。しかし、なかなかそうはいかないものです。
今回も現役教師の方から、子どもをどのように見ているのかということを聞いてみました。
先生の子どもに対する対応方法に疑問を持っている方や、先生として働いていて子どもや保護者への対応に悩んでいる方に少しでも参考になればと思います。
保護者と子どもの関係 子どもの後には保護者がいることを忘れない
学級にいる子どもの後ろには保護者がいます。
保護者のご機嫌を伺いながら教員生活を送っているという現状に、最近気づいてしまいました。
保護者からのクレーム 子どもに対しての見方が変わる
あるとき、私に一本の電話がかかってきました。それは保護者からの私に対するクレームでした。
学級にいる子どもの数が多くなれば多くなるほど、クレームが来る可能性は当然高くなりまし、全員に私の指導法が満足には行き届くわけは無いので、ある意味仕方の無いことではあります。
現在の学校現場では、クレームは日常茶飯事かもしれません。勿論、全くクレームがこない教師もいます。子どもからも保護者からも好かれる教師はいます。
話は戻りますが、そのクレームが来て依頼、クレーム元の子どもを私は、「色眼鏡」で見るようになってしまいました。
「この子どもに何かを言ったりしたりすれば、また保護者から何か言われる」
そう思ってしまうようになってしまいました。
子どもが注意されなくなるリスク
そんなことを先輩教師に相談したところ、次のような回答が帰ってきました。
「それは自然なことだよ。教師も人間だからね。文句ばかり言ってくる保護者には腹が立つし、その子どもを意識してしまうよ。親は気づかないのかな?クレームをするということは、自分の子どもを逆に追い詰めてしまうことだってことが。」
実際、クレーム後、私はその子どもに突っ込んだことができなくなりました。強い口調で注意することもできなくなりました。
しかし、それが本当によいことなのでしょうか?
悪いことをしたらしっかりと指導をしなければいけないと思うのです。
実は有名なクレーマーだった
その保護者は有名なクレーマーでした。毎年、担任の教師に何かとクレームを言ってくるそうです。
それがわかったとしても、今回のような状況で、まだその子に注意できる教師がいますか?クレームが来ると分かっていて、注意できますか?余程ひどく悪いことをしない限り、注意することは教師側からはなくなります。
本当に、その子のためになるのでしょうか?なるわけありません。
人気のある先生はそれなりの理由がある
教師にも保護者にも人気のある先輩教師にも相談をしてみました。するとこんな回答がかえってきました。
「保護者のために教育をしているわけではない。子どものためにしている。だから、子どもが悪いことをすれば普通に怒る。保護者が何を言ってこようが関係ない。その時に、反論できるだけの材料を用意しておけばいい。反論といっても強い口調ではまずい。丁寧にゆっくりと説明をする。でも一番の基本は、保護者と学年はじめで仲良くなってしまうこと。これが一番大事。そうすればちょっとのことではクレームはこない。」
なるほどと思いました。
保護者と一緒に子どもを育てているといった環境をこちら側から作ればよいのです。難しいことかもしれませんが、挑戦したいと思います。
保護者対応が大変という意見があるが
学校の先生をしている上で大変と思われることの1つが「保護者対応」です。
今回インタビューをさせてもらった先生のように感じている先生は多いと思います。
しかし一方で、生徒との関係も良好で、保護者からクレームがほとんどない先生がいることも事実です。
あまり表立って行動していないのかもしれませんが、そのような先生はそれなりの行動をしているケースが多いです。
密にコンタクトを取っている
クレームの少ない先生の特徴としては、密に保護者とコンタクトを取っていることがあります。
しばらく学級運営をしていると、どの子どもが問題を起こしやすいのかということがわかってきます。わかった段階でその子どもの保護者とコミュニケーションを取っていくようにするのです。
もちろんいろいろな親がいるため、コミュニケーションを避けようとする人もいます。それでも何かあるごとにコミュニケーションを取っていくのです。
また親とコミュニケーションを取り続けていると、どういった親なのかを判断することもできます。これによって対応を考えているのです。
先生の中には問題を避けたいと思う人も多い
先生の中には、問題を避けたいと思っている人は多いです。
よく問題を起こす生徒の担任が言った言葉です。
「今年我慢して来年の先生にパスすればよい」
このような考えの先生は少なからずいます。
変に子どもに注意をし、保護者や学校を巻き込むと、その対応の時間が増えてしまいます。学年で話し合う時間も増えますし、教頭先生や校長先生を巻き込んでの話も必要となるでしょう。
さらに保護者との話し合いも出てきます。
これによって膨大な時間が割かれるのです。
それであれば、変に大事にせず1年間を何となくやり過ごせば、問題に対応する時間を割く必要もありませんし、悩む必要もありません。早く帰ることもできます。
これがわかっている先生は、問題を起こす生徒に対しても受け流すこともあるのです。
問題によって自分の評価が下がることを懸念する
保護者を巻き込んだトラブルとなることは、自分の評価を下げるものだと思う先生もいます。
評価を下げることで、自分の意見が他の先生に通りづらくなることを恐れているのです。
また将来的に教頭や校長になるための弊害になってしまうと考えているのかもしれません。
極論 生徒を更生させても評価にそれほど影響しない
問題行動をする子どもは一定数います。
その生徒を全力で更生させたとしましょう。しかしそれによって先生の立場が優遇されるとか、給与が上がるとかいったことはありません。
逆に「あの先生は問題のある生徒をまとめてくれる。では次の年度も問題のある生徒はあの先生に担当してもらおう」というようになる可能性が高まるのです。
そう考えると、「問題のある生徒は先送りにしよう」と考える先生がいても不思議ではないのです。
まとめ
今回は私が教員として働いていた経験からお話しさせてもらいました。
いろいろな先生がいます。子どものことを思って仕事をしている人もいますし、仕事として先生をしている人もいます。
そのため問題に真正面から取り組む人もいますし、避けようと考える人もいます。
ただ先生をしていた経験からいえることは、「あまり学校に意見を言いすぎない方がよい」ということです。本当に良くないことがあったときのみ言った方がよいと思います。
正直難しい所ではありますが、自分の子どもが先生から色眼鏡で見られるとあまり良い結果にはならない気がします。
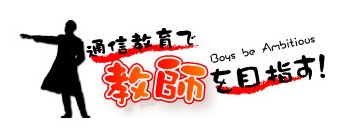



取得できる通信大学を検索
取得できる通信大学を検索