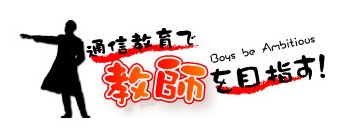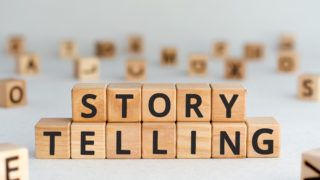ここではさまざまな教育問題に、当サイト管理人独自の視点から触れていきたいと思います。
そして教員の不祥事が多い理由、不祥事を起こさないようにするべきことを紹介しています。完全に私見です。
教員の不祥事が多い6つの要因
教員の不祥事が非常に多く取りだたされています。
なぜ教員は不祥事が多いのでしょうか?それは以下の理由が考えられます。
- 教師という立場
- 社会経験の少なさ・経験不足
- 仕事の多忙化
- 職場の同僚や保護者との人間関係の問題
- 採用基準の甘さ
- 管理体制
当サイト管理人は、学校でも学習塾でも長年において携わってきました。その経験をもとにお話しさせていただきます。
すべての教員が問題というわけではない
前提としてですが、すべての教員が問題というわけではありません。
子どものことを考え一生懸命仕事をしている人もいるのです。
ただしそもそも教員という仕事は社会的イメージがあります。イメージがあるからこそ、それを逸脱する行動をすると目立つのです。
学生時代のイメージから離れられない先生
学生時代の良い思い出に浸り続けている人がいます。そしてそこから抜け出せずにいることも。
そのため考えが学生時代のまま止まってしまっている人も。
体は大きくなっているのに考えは学生のような。ピーターパンシンドロームのような状態なのかもしれません。
よって子どもであれば注意で済むようなことを、大人になってもしてしまう、そしてその人は先生・・・ということで世間の注目を浴びてしまうことも。
教師という立場を勘違いしてしまっている人がいる
教師という立場を勘違いしてしまっている人はいます。
立場が勘違いを生んでしまっている可能性
教室の中では先生が一番の年配です。そして生徒に物事を教える立場です。
するとまるで自分が偉くなったかのような錯覚を起こしてしまうのです。有名な実験でいうと「スタンフォード監獄実験」です。
人間は立場によって考え方や行動が変わってくるというものです。
これは少し極端な例かもしれません。また捏造いう噂もあります。ただしこのような状態になってしまうことがあります。
たとえば学校のクラスを例にしてみましょう。学級委員や班長になると、態度がしっかりとする生徒を目にしたことはないでしょうか?
そのほかでは、たとえば警察官は妙に偉そうに思えることはないでしょうか?
このような感じで、人は立場によって考え方や行動が変わることがあるのです。
よって教師も同じことがいえます。妙に偉そうな態度になってしまうことがあるのです。それにより行き過ぎた問題行動や問題発言をしてしまう可能性があるのです。
社会経験の少なさ・経験不足
教員の多くは大学を卒業してすぐに学校に就職しています。
つまり社会人経験がないのです。
先生は一般社会のルールから離れたところにいる
先生の多くはずっと学校というルールの中にいます。
そのため、一般的な会社がどのようなルールで動いているのか、どのような思いで多くの人が仕事をしているのかを身を持って体験したことがないのです。
よって小学校、中学校、高校、大学、そして就職先の学校と、ずっと学校の中で生活をしている状態となるのです。
学校のルールがすべてのルールなのです。
この後にもお話ししますが、世の中を知らないがために、まるで先生の仕事が一番大変化のような思いを持つ人が意外と多いです。
クラスで教えている生徒の保護者は、一般社会で生活している人たちです。そして教えている子どもも、そのほとんどは将来学校の先生以外の仕事に就きます。
社会に出たことのない先生が、そういった人たちと関わっているため、どうしても周りから指摘を受けやすくなってしまうのです。
仕事の多忙化
学校の先生の仕事は忙しい・・・とされています。しかし学校で働いていましたが、正直そこまで大変ではないです。
忙しい先生がいることは事実です。しかしそれは自分で仕事を受けてしまっているという点、そして先生の仕事は自分のさじ加減でいくらでも忙しくできるといった点です。
意外と余裕はある
結論からいうと、先生の仕事は意外と余裕があります。そして定時で帰ることは可能です。
またもし残ることを強要されるようなことがあれば、問題にすればよいだけの話です。問題にしたとしても地方公務員である教員は解雇されることはありません。
しかし多くの先生はそうはしません。なぜなら「真面目だから」、そして「波風を立てたくないから」です。


仕事が終わらないから帰れない・・・という人は多いですが、以下の理由が考えられます。
- 自分で生徒のためにと作業を増やしている。
- 周りの先生からの頼みを断れない。
- 仕事のスピードが遅い。要領が悪い。
結構これらに該当する先生は多いです。
先生はいい意味で不真面目になるべきだと思う
当サイト内でもよく言っていますが、先生はもっと不真面目になってもよいと思います。
いろいろ仕事を増やしこなすことで評価を得ようとする先生はいます。また学校によっては遅くまで残って仕事をすることを美徳と考える傾向にあるケースもあります。
結論、自分の評価を高めたいという思いがあるためだと思います。自分でそのような状況にしておきながら「仕事が忙しい」という人がいます。
また忙しいことをほかの先生にも強要したり、プレッシャーを与えてしまっていることがあります。
忙しくしている先生は自ら忙しくしていることが結構あります。それを気にする必要はありません。
その結果、心身に支障をきたしてしまっても誰も何もしてくれません。場合によっては仕事ができなくなってしまいます。
生徒のためにも学校のためにも一番は、先生自身が心身健康でいて楽しく授業をすることです。これを忘れてしまっている先生は多いと思います。
いい意味で不真面目になったほうがよいですし、それでも先生としてやっていけます。
時間があるからこそ余計なことをする
先生は忙しいといわれていますが、私は経験上そのようなことはないと思っています。
逆に時間に余裕があるからこそ、余計なことをしてしまう人もいるかと思います。
先生には決められた残業時間はありません。残業するのもしないのも自由です。時間的余裕があるのです。
そのためゆっくり仕事をする人もいるし、どんどん帰りたい人はどんどん仕事を終わらせます。
時間にゆとりがあるため、他の先生に意地悪をする人もいますし、不祥事を起こす人もいます。
もし仕事に追われていたら、そんなことをしている暇はないのです。
それを私自身目にしてきたため、「教員=忙しい説」は賛同しかねるのです。よほど民間の会社の方が忙しいです。
職場の同僚や生徒、保護者との人間関係の問題
先生として円滑に仕事をするのであれば、他の先生方とのコミュニケーションは非常に大切です。
また生徒、そして保護者とのコミュニケーションも大切となります。
同僚との関係性を良好にする必要がある
同僚の先生とのコミュニケーションは非常に大事です。
基本は同じ学年の先生と連携して仕事をすることが多いのですが、委員会、分掌、イベントなどでほかの先生と関係を持つことは意外とあります。
その際に、上手く連携が取れていないと助けることもできないし、助けられることもできません。
とくに教員経験が浅いと、先輩教員にいろいろ教えてもらいながら仕事をすることになると思います。
その際、コミュニケーションがうまく図れないとうまく仕事ができなくなってしまうのです。
先生の中には、向こうから助け舟を出してくれるケースもありますが、すべての先生がそうとは限りません。
他の仕事を抱えながらなので、ほかの人に構っている余裕はないという先生も多いです。


生徒・保護者との関係構築
生徒と保護者との関係は、きちんと構築しておいた方がよいです。
よかれと思った言動も、受け取り手次第によってはさまざまな解釈をされます。それにより思わぬトラブルに発展することは多々あります。
しかし関係がきちんと構築できていると、トラブルは意外と回避することができます。
関係を強化するためにも自分をさらけ出す
実体験の話ですが、生徒とも保護者とも関係を強化するためには、自分をさらけ出した方がよいです。
うわべだけの付き合いでは、関係が希薄なものとなってしまいます。
たとえば保護者に対しては、常日頃から連絡を取っておいた方がよいでしょう。これは連絡帳でもよいですし電話でもよいです。
出来ればたまにでも電話で直接話すと関係を作ることができます。
ただしすべては人によります。連絡を頻繁にした方がよい人もいればそうではない人もいます。
それを見極めるためには、人間観察力が必要となってくると思います。


採用基準の甘さ
教員採用試験は学力検査といっても過言ではありません。
結局のところペーパー試験で高得点を取ることに重きを置いています。
よって勉強ばかりしてきて、人との関わりを持ってこなかった人でも合格をしてしまうわけです。
学校の先生に必要なのは学力か?人間性か?
学校の先生として勉強を教える力は大切ではあります。しかしこれはある程度後付けでもなんとかなります。
しかし社会に出てから人間との付き合い方を学ぶというのは、なかなか難しいものです。そのため子どものころ、たくさんの人と遊んでいた人や、さまざまな経験をしてきた人の方が、教育者としては適しているかと思います。
ところがその面を、現在の採用試験ではそこまで重要視しません。点数に反映しづらいといったこともあるでしょう。
また採用している側が、学力で教員採用試験をパスしてきた人たち、または文部科学省です。
学力が重視されてしまうのは致し方ないのですが、そのあたりを変えていかないと教員の不祥事の数は減らないことでしょう。
学力と人間性は比例しないと思うのです。
管理体制
教員の不祥事には管理体制の甘さもあると思います。
校長や教頭などが職員に対して、教員とはどうあるべきかをしっかりと伝える必要があります。
「仕事柄周りから見られている」ということを徹底するべきでしょう。
ただしこのようなことを言わなければわからない人が教員になってしまうこと自体が問題です。
つまり話は戻り、採用段階でしっかりとしたふるいにかける必要があるということになります。
まとめ
このように学校の先生に不祥事が多い理由はいくつか挙げられます。
しかしどれも不祥事を起こしてよい理由にはなりません。起こすのであれば、はじめから人から見られる先生(地方公務員)にならなければよいと思うのです。
一生懸命子どものことを思って行動をしている先生もいます。そういった人たちにはもっと良い待遇を与えてほしいと思います。
しかしその待遇を考えるのは、勉強ばかりしてきた人たちです。だから教育制度はなかなか良い方向へ進まないのでしょう。
とはいっても、ここまでお話ししてきたように、先生という仕事は大変すぎる、辛すぎるといったことはありません。一般社会のブラック企業の方が何倍もつらいです。
そしてやりがいのある職業です。個人的な意見ですが、これまでしてきた仕事の中でもトップクラスで面白くやりがいのある仕事だと思います。
問題は「自分がどれだけ楽しめるか」です。自分の居場所(環境)は自分で用意するのです。